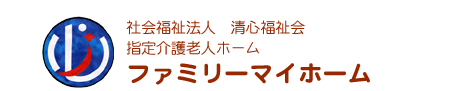ブログ
父の日
6月15日(日) 「ファミリーマイホームのお父様」に、癒しの空間を提供するべく「バー・ファミリーマイホーム」を臨時開店させていただきました。ファミーマイホームでは、利用者様自らが選択する機会を少しでも提供することを介護方針に掲げております。今回もさまざまなドリンクや軽食の中から、利用者様が注文したメニューを提供させていただきました。
2025/06/15
ミニ運動会
今年もファミリーマイホームでは、日々の健康増進とともに、若かりし日の思い出を回想していただくために、1階食堂でミニ運動会を開催いたしました。紅組・白組に分かれての白熱した戦いが繰り広げられました。その様子をご覧ください!
2025/06/06
春のバスハイク
始まりました、春のバスハイク!
ファミリーマイホームでは、今年度も春2回・秋2回外出行事の一環としてバスハイクを企画し、実施しております。今回の春のバスハイクは、あいにくの天候だったため、高尾山方面にある「アニマルカフェ」に行くこととしました。昼食は道中の和食レストランを予約し、利用者様が各々に食べたいものを注文していただきました。コロナ禍では、外出することもままならない状況でしたが、そのような状況も今は昔。これからも、利用者様が少しでも地域へ出かける・参画する機会を設けていきたいと考えています。バスハイクにご協力いただきました関係者の皆様、この場を借りて改めて感謝申し上げます。
ファミリーマイホームでは、今年度も春2回・秋2回外出行事の一環としてバスハイクを企画し、実施しております。今回の春のバスハイクは、あいにくの天候だったため、高尾山方面にある「アニマルカフェ」に行くこととしました。昼食は道中の和食レストランを予約し、利用者様が各々に食べたいものを注文していただきました。コロナ禍では、外出することもままならない状況でしたが、そのような状況も今は昔。これからも、利用者様が少しでも地域へ出かける・参画する機会を設けていきたいと考えています。バスハイクにご協力いただきました関係者の皆様、この場を借りて改めて感謝申し上げます。
2025/05/30
母の日
5月18日(日) 「ファミリーマイホームの母」の皆様に、素敵な?舞台劇を披露させていただきました。また、利用者の皆さんへのささやかなプレゼントとして、カーネーションの花束と入浴後に私用していただく美容グッズを用意させていただきました。
行事前に発熱などの利用者が複数名おられたため、感染予防の観点から、2階食堂にて一部内容を縮小しての開催となりましたが、利用者様のリアクションも上々の様子でした。
行事前に発熱などの利用者が複数名おられたため、感染予防の観点から、2階食堂にて一部内容を縮小しての開催となりましたが、利用者様のリアクションも上々の様子でした。
2025/05/18
外出の日(近隣散歩)
ファミリーマイホームでは、少しでも利用者様の外出支援を行うべく、春・秋のバスハイク、第5土曜日には「外出の日」の行事を予定しております。本日は、天気も良かったので、マスクを着用し感染対策を行って、「道の駅八王子滝山」まで散歩してきました。コロナ禍でなかなか外出もままならない日々が続いていましたので、心地よい陽の光とさわやかな風に包まれ、身も心もリフレッシュすることができ、とても楽しいひと時を過ごすことができました。
2025/04/27
春のお花見ドライブ
桜満開の季節がやってまいりました。ファミーマイホームの正面玄関脇の陽光桜も満開になりました。それだけでは飽き足らず、新滝山街道沿いまでドライブを実施しました。桜の淡いピンクの景色と春の風を感じながら悠久の時の流れに身をまかせていると、利用者様と一緒に別世界に紛れ込んでしまったかと錯覚してしまうひと時でした。
2025/04/06
滝山城址桜まつりへの参加
滝山城址は、戦国時代に北條氏照が居城した山城です。北側には多摩川が見渡せ、自然の地形を巧みに利用しており、ソメイヨシノや山桜が5000本咲き乱れる名称となっています。毎年、4月第1土日曜日に本丸跡地で桜祭りが開催され、そのお祝いをお届けに利用者様と一緒に参加致しました。さまざまなイベントも開催されており、甲冑試着の体験もさせていただきました。
2025/04/05
祝!ファミリーマイホーム開設記念日(リニューアルオープン記念)
ファミリーマイホームは、平成7年(1995年)4月1日に開設し今年で31年目を迎えます。30周年記念の節目の記念日として、サプライズゲストとして「アニマルイベント企画」様をお招きし、初めてアニマルショーを開催しました。おさるさん・ワンちゃんの素晴らしいパフォーマンスに感激し、ふれあいタイムで癒され、素晴らしい1日となりました。
2025/04/01
春のお花見
令和2年に、ファミリーマイホームのリニューアル工事が完了した際に植樹した「陽光桜」が満開になりました。施設の玄関で花見ができる、この場面を思い浮かべて早5年、陽光桜が見事に育ってくれています。
車で少し出かけると、桜並木が素晴らしい景色を演出してくれています。少し外出するだけでも、気持ちが華やぐことを実感できます。
車で少し出かけると、桜並木が素晴らしい景色を演出してくれています。少し外出するだけでも、気持ちが華やぐことを実感できます。
2025/03/30
日頃のお手伝いに感謝の気持ちをこめた御礼
ファミリーマイホームなどの老人ホームでは、利用者様におしぼりや食事用のエプロンなどをたたんでもらうことを日課の活動としていることがあります。
ファミリーマイホームでも、利用者様が率先してタオルなどをたたんでいただく場面が毎日のようにあります。入所した後も職員とともに毎日お手伝いしてくださる利用者様に対して、毎年1回ですが御礼を込めて感謝祭という食事会を主催しており、近所にある増田屋さんの出前を提供させていただきました。皆様より事前にお品書きの中から、お好きな物を選んでいただき、カロリーなども気にせず、おなか一杯召し上がっていただきました。日頃のご厚意に対して感謝の気持ちを伝えさせていただくとともに、施設に入所しても毎日生きがいを持って生活することを実践されている利用者様へ勇気をいただける、大変有意義な時間となりました。
ファミリーマイホームでも、利用者様が率先してタオルなどをたたんでいただく場面が毎日のようにあります。入所した後も職員とともに毎日お手伝いしてくださる利用者様に対して、毎年1回ですが御礼を込めて感謝祭という食事会を主催しており、近所にある増田屋さんの出前を提供させていただきました。皆様より事前にお品書きの中から、お好きな物を選んでいただき、カロリーなども気にせず、おなか一杯召し上がっていただきました。日頃のご厚意に対して感謝の気持ちを伝えさせていただくとともに、施設に入所しても毎日生きがいを持って生活することを実践されている利用者様へ勇気をいただける、大変有意義な時間となりました。
2025/03/24